研究・開発の窓 COLUMN
研究・開発の窓

薬物の代謝速度や相互作用に関与する小胞体膜トランスポーターの機能を解明する
名古屋市立大学大学院 薬学研究科 教授
荒川大氏薬物の小胞体への取り込みを担うトランスポーター「OAT2」体内に入った薬物は2段階の化学反応を経て代謝・排泄されるが、第II相反応で中心的な役割を果たすのが肝細胞で行われるグルクロン酸抱合反応である。名古屋市立大学大学院薬学研究科教授の荒川大氏(医療機能薬学専攻レギュラトリーサイエンス分野)は、グルクロン酸抱合反応において、小胞体膜トランスポーターが代謝酵素や薬物の小胞体内への取り込みや排出を担い、薬物の代謝や相互作用発現に...

消化管全体の生理環境と薬物動態を考慮した革新的な薬物吸収性予測モデルを開発する
昭和薬科大学 薬学部 教授 白坂善之氏
(薬剤学研究室)カオスのような消化管全体での薬物動態を定量的に解析 医薬品のモダリティが多様化、複雑化し、売上高上位の医薬品の大半を注射薬が占めるようになった。しかし、患者のQOLや経済性の観点から経口医薬品へのニーズはますます高まっている。薬物動態研究を専門とする昭和薬科大学薬学部教授の白坂善之氏(薬剤学研究室)は、「創薬において、経口医薬品こそ、目指すべき着地点である」と強調する。 こうした背景を踏まえて、白坂氏が挑戦している...

プロテオーム解析を起点に老化関連疾患の病態機序や健康長寿の因子を探索
東京都健康長寿医療センター研究所 研究部長 三浦ゆり氏(老化機構研究チーム プロテオーム研究)加齢性中膜変性症の分子メカニズムを解明 東京都健康長寿医療センター研究所・老化機構研究チームのプロテオーム研究テーマは、プロテオーム解析の手法を用いて老化関連疾患や健康長寿に関連するタンパク質の探索的研究を行うことだ。研究部長の三浦ゆり氏は、いわゆるオミクス研究と称される生体分子の網羅的研究に共通する特長として、「既存の仮説に囚われることなく新しい研究ができる」「生命現象の全体を把握することができる」の2点を挙げ、...
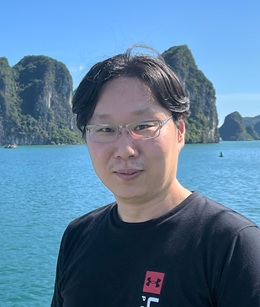
バイオ医薬品の経口投与や効率的脳内移行を実現する「組織関門透過ペプチド」を発見
熊本大学大学院 生命科学研究部 准教授
伊藤慎悟氏高分子創薬モダリティの組織関門透過の課題解決を目指す 近年、バイオ医薬品が数多く上市されているが、高分子であるため経口投与や脳内移行が難しいことが課題となっている。熊本大学大学院生命科学研究部微生物薬学分野・准教授の伊藤慎悟氏らの研究グループは、小腸と脳の関門を越える新たなDDS(ドラッグ・デリバリー・システム)キャリア「組織関門透過ペプチド(TBPP)」を発見し、実用化に向けた研究を進めている。 伊藤氏は「インス...

食品の機能性成分を分子・細胞レベルで解析し、「食による病気の予防」を目指す
群馬大学大学院 食健康科学研究科・理工学府 教授 薩秀夫氏腸管上皮細胞モデルなどを用いて、食品成分の作用を解析 群馬大学大学院教授の薩秀夫氏(食健康科学研究科・理工学府 理工学部・食品工学プログラム・食品機能学研究室)は、モデル細胞を用いた機能性食品成分の探索および解析研究を通じて、「食で病気を予防する」ことを目指す研究者だ。「食品を開発する企業はそれぞれ独自の素材を有しているが、生体への作用やそのメカニズムを評価する適切な実験系を持たないことが多い。企業との共同研究で食...

新たな遺伝子改変技術で長鎖ノックインマウスの高効率な作製に挑む
東京大学大学院農学生命科学研究科
助教 藤井渉氏CRISPR/Cas9で世界に先駆けて受精卵から遺伝子改変マウスの系統作出を報告 東京大学大学院農学生命科学研究科の藤井渉助教(獣医学専攻・実験動物学研究室)は、ゲノム編集技術CRISPR/Cas9による受精卵を介した遺伝子改変マウス系統の作出を世界に先駆けて報告した研究者で、2023年に株式会社ケー・エー・シー創立45周年記念研究助成を受賞し、「新たな遺伝子改変技術による長鎖ノックインマウスの高効率な作製系の開発...

