研究・開発の窓 COLUMN
研究・開発の窓

製薬企業ニーズに応える国産生体模倣システムを製品化し、日本発の創薬を支援
筑波大学 生命環境学群 伊藤弓弦教授(生命地球科学研究群 生命環境系)動物実験では問題がなかったにもかかわらず、治験では重篤な副作用が発現することがある。データ蓄積の乏しい新たな創薬モダリティでは特にその傾向が強く、前臨床段階で毒性や有効性を精緻に予測する技術の開発が求められている。 筑波大学の伊藤弓弦教授を研究代表者とするAMEDの「製品化戦略に基づいた、国産MPS(Microphysiological System=生体模倣システム)による創薬プラットフォームの実証研究」は、まさに製薬企業...

がんや自己免疫疾患の発症にも関わる「直鎖状ユビキチン鎖」を発見
京都大学大学院医学研究科 岩井一宏教授(細胞機能制御学分野)ユビキチンは、タンパク質の翻訳後修飾系の一つであるが、多くの人はタンパク質の分解に関わるユビキチン―プロテアソームシステムを想起することだろう。だが、現在では、ユビキチン修飾系はタンパク質の分解のみならず、さまざまな生体機能の制御系として機能していることが分かってきている。京都大学大学院医学研究科の岩井一宏教授(細胞機能制御学分野)らが発見した、特異な構造のユビキチン「直鎖状ユビキチン鎖」は、がんや自己免疫疾患の発症にも関与...

ラマン顕微鏡で細胞組織内分子を可視化する
大阪大学大学院工学研究科 藤田克昌教授、 産総研先端フォトニクス・バイオセンシングオープンイノベーションラボラトリ 藤田聡史副ラボ長2022年8月、国の研究機関である国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)と大阪大学の共同研究により、ラマン顕微鏡(写真)という技術を用いて、細胞を壊さず、標識することもなく、肝細胞内の薬物代謝活性を可視化することに成功したという成果が発表された。ラマン顕微鏡が、創薬や診断技術、再生医療などの生命科学分野の技術開発に貢献する可能性を実証した研究成果として、脚光を浴びている。 大阪大学吹田キャンパスの...

血液脳関門を再現するヒトのミニブレインを開発
東京薬科大学薬学部 降幡知巳教授(医療薬学科個別化薬物治療学教室)血液脳関門は、今も脳疾患治療薬などを開発する上で分厚い壁となっている。東京薬科大学薬学部の降幡知巳教授(医療薬学科個別化薬物治療学教室)は、オリジナルのヒト不死化細胞を使って、ミクロサイズの血液脳関門の生体模倣システムの開発に成功し、国内外の研究機関や製薬企業から大きな注目を浴びている。生体外で幹細胞などから3次元的に培養した臓器モデルは、通常、“オルガノイド”と呼ばれるが、降幡教授が作製したヒトの脳モデルはオルガノイドとは...
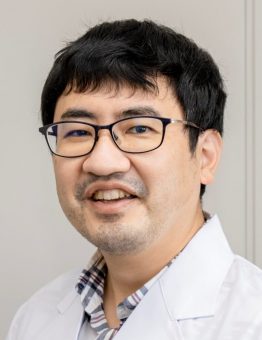
ヒト手術残余検体を用いた消化管の薬物吸収評価系を確立する
北里大学薬学部 前田和哉教授(薬剤学教室)経口薬を開発する上で、消化管からの薬物吸収性を評価することは極めて重要だ。しかし、これまで、創薬の過程において繁用されるin vitro実験系は大腸がん由来の細胞株を用いたものであり、実際に薬物吸収が行われる部位である小腸の正常細胞は用いられていなかった。北里大学の前田和哉教授(薬学部薬剤学教室)は、ヒト小腸の手術残余検体を活用した実験系を構築し、より精度の高い薬物吸収性予測を実現する研究を進めている。前田教授の専門分野は薬...

プロスタグランジン産生機構の研究から、新たなNSAIDsや抗がん薬の標的を見つける
昭和大学薬学部 原 俊太郎教授(社会健康薬学講座衛生薬学部門)NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)は、アラキドン酸の代謝経路で働くシクロオキシゲナーゼ(COX)を阻害してプロスタグランジン類の産生を抑制し、解熱、鎮痛、抗炎症効果を発揮する薬だ。昭和大学薬学部の原俊太郎教授(社会健康薬学講座衛生薬学部門)らは、今日的な手法でプロスタグランジン産生機構の研究を推し進め、副作用の少ないNSAIDsや、新しい作用を有する薬の開発につながる創薬標的を見出す研究を続けている。衛生薬学は、疾病予防...

